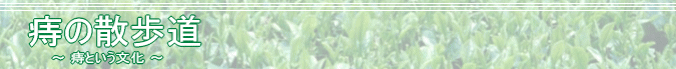
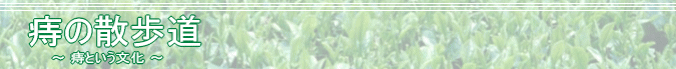
| 「明暗」 夏目漱石 漱石の死とともに未完成に終ったこの作品は、文字通り漱石文学の総決算で、自然主義に近い客観的態度で人間の醜悪を余りなく描破しながら、しかも漱石が背後に意図したものは、いわゆる「則天去私」という真実の生き方であった。終りの方に現われる清子という女性の影像がそれを暗示している。大正5年作。 昭和五十九年十月三十日 改訂二十一版発行 角川文庫 「明暗」夏目漱石 のカバーから引用 この小説は、「痔」の診察の場面から始まります。そして、入院、手術などを背景として物語が進行していきます。漱石自身が痔であり、手術を2回しております。漱石の痔は、痔の中でも痔ろうという疾患でした。この痔ろうに関する体験をこの小説「明暗」、そして日記、書簡、俳句などに残しています。 漱石は、なぜかこの「明暗」では、痔又は痔ろうという病名を使用せず、単に「病気」と表記しています。 以下、同上角川文庫「明暗」から診察と手術の場面のみを引用します。(長い引用になります。) なお、この夏目漱石の痔については、本「痔の散歩道」の「日記・書簡」と「痔に悩んだ人々①」にも記述しています。こちらも参照してください。 ■「明暗」 冒頭(診察場面) 一 医者は 「やっぱり穴が腸まで続いているんでした。このまえ探った時は、途中に 「そうしてそれが腸まで続いているんですか」 「そうです。 津田の顔には苦笑のうちに淡く盛り上げられた失望の色が見えた。医者は白いだぶだぶした上着の前に両手を組み合わせたまま、ちょっと首を傾けた。その様子が「お気の毒ですが事実だからしかたがありません。医者は自分の職業に対してうそをつくわけにゆかないんですから」という意味に受け取れた。 津田は無言のまま帯を締め直して、 「腸まで続いているとすると、なおりっこないんですか」 「そんなことはありません」 医者は活■《かつぱつ ■=さんずいに發》にまた無雑作に津田の言葉を否定した。あわせて彼の気分をも否定するごとくに。 「ただ今までのように穴の 「根本的の治療というと」 「切開です。切開して穴と腸といっしょにしてしまうんです。すると天然自然 津田は黙ってうなずいた。彼のそばには南側の窓下に据えられたテーブルの上に一台の顕微鏡が載っていた。医者と懇意な彼はさっき診察所へはいった時、物珍らしさに、それをのぞかせてもらったのである。その時八百五十倍の鏡の底に映ったものは、まるで図に 津田は袴をはいてしまって、そのテーブルの上に置いた皮の紙入を取り上げた時、ふとこの細菌のことを思い出した。すると連想が急に彼の胸を不安にした。診察所を出るべく紙入を 「もし結核性のものだとすると、たとい今おっしゃったような根本的な手術をして、細い 「結核性ならだめ」です。それからそれへと穴を掘って奥の方へ進んでゆくんだから、口元だけ治療したって役にゃ立ちません」 津田は思わず 「 「いえ、結核性じゃありません」 津田は相手の言葉にどれほどの真実さがあるかを確かめようとして、ちょっと目を医者の上に据えた。医者は動かなかった。 「どうしてそれがわかるんですか。ただの診断でわかるんですか」 「ええ。 その時看護婦が津田のあとに回った患者の名前を 「じゃいつその根本的手術をやっていただけるでしょう」 「いつでも。 津田は自分の都合をよく考えてから日取りをきめることにして室外に出た。 原文注釈 ※医者は探りを入れた後で・・・・・・ 漱石は明治四十四年(一九一一)、大阪・和歌山などを講演旅行後九月十四日帰京、神田区錦町一丁目にあった佐藤病院で痔の手術を受け、翌年春まで通院、さらにその年の九月二十六日から十月二日まで再手術のためこの病院に入院した。明治四十四年十一月から大正元年(一九一二)十月までの日記には、この時の病院通いや病院生活で聞いた話についての詳しいメモがあり、それらがこの「明暗」の材料として用いられている。 ※瘢痕 傷などが治癒したあと。 (手術場面) 四二 「リチネ※はお飲みでしたろうね」 医者は 「飲みましたが思ったほど 「じゃもう一度 浣腸の結果も十分でなかった。 津田はそれなり手術台に上って仰向けに寝た。冷たい防水布がじかに皮膚に触れた時、彼は思わず冷やりとした。堅い 「コカインだけでやります。なにたいして痛いことはないでしょう。もし、注射がだめだったら、奥の方へ薬を吹き込みながら進んでゆくつもりです。それでたぶんできそうですから」 局部を消毒しながらこんなことを言う医者の言葉を、津田は恐ろしいようなまたなんでもないような一種の心持で聞いた。 「どんなです。痛かないでしょう」 医者の質問には十分の自信があった。津田は天井を見ながら答えた。 「痛かありません。しかし重い感じだけはあります」 その重い感じというのを、どう言い現わしていいか、彼には適当な言葉がなかった。無神経な地面が人間の手で掘り割られる時、ひょっとしたらこんな感じを起こしはしまいかという空想が、ひょっくり彼の頭に浮かんだ。 「どうも妙な感じです。説明のできないような」 「そうですか。我慢できますか」 途中で脳貧血でも起こされては困ると思ったらしい医者の言葉つきが、なんでもない彼をかえって不安にした。こういう場合予防のために葡萄酒《ぶどうしゆ》などを飲まされるものかどうか彼はまったく知らなかったが、なにしろ特別の手当を受けることはいやであった。 「大丈夫です」 「そうですか。もうじきです」 こういう会話を患者と取り換わせながら、間断なく手を働かせている医者の態度には、熟練からのみ来る 切れ物の 彼は、大きな目をあいて天井を見た。その天井の上にはきれいに着飾ったお延がいた。そのお延が今なにを考えているか、なにをしているか、彼にはまるでわからなかった。彼は下から大きな声を出して、彼女を呼んでみたくなった。すると足の方で医者の声がした。 「やっと済みました」 むやみにガーゼを詰め込まれる、こそばゆい感じのしたあとで、医者はまた言った。 「 最後の注意とともに、津田はようやく手術台からおろされた。 ※リチネ Ricinus(ラテン語)。ヒマシ油。下剤の一種。当時、薬局方による薬品名はラテン語であった。 同上 「明暗」から全文引用。 一部、原文と表記が異なるところがあります。 なお、肛門科医の衣笠昭氏は、この夏目漱石の診察・手術に関し、日本大腸肛門病学会誌で次のように記述しています。(こちらも、長い引用になります。) 漱石は明治44年(1911)9月14日、講演旅行より帰京して神田錦町にあった佐藤医院で痔の手術を受けたという。この手術は肛門周囲膿瘍の切開であろう。その後翌年の9月に入院し、痔瘻の手術を受けたとされる。 この経験を基にして「明暗」には主人公が痔瘻の診断・手術を受け、術後の状況が細かく描写されており、明治後期より大正時代の手術がどのようなものであったかを推察できるので、その概略を解釈してみることとする。 「明暗」の第1章の冒頭では主人公津田が痔瘻の診断を受けるところから始まる。医師は診察の結果を説明し、痔瘻の治療法についての話をしている。『ただ今のように穴の掃除ばかりしていては駄目なんです。それじゃいつまで経っても肉の上がりっこはないから、今度は治療法を変えて根本的の手術をひと思いにやるよりほかに仕方がありませんね』『切開です。切開して腸と穴とをいっしょにしてしまうんです。すると天然自然割かれた面の両側が癒着して来ますから、まあ本式に癒るようになるんです。』要するに切開解放術式の説明をしているが、当時痔瘻は結核であるとの説が流布されており、また実際に結核性痔瘻が多かったであろう。主人公はこの点を質問しているが、医師は結核性ではないと断言し現在でいうインフォームド コンセントを行っている。 手術当日主人公は手術台に上り、仰向けに寝た。体位は恐らく砕石位であったであろう。『コカインだけでやります。なに大して痛い事はないでしょう。もし注射が駄目だったり、奥の方へ薬を吹き込みながら進んで行くつもりです。それで多分できそうですから』局所麻酔はよく効き、医師の質問に対し『痛かありません。しかし重い感じはあります』と答えている。手術は約28分で終了した。恐らく低位筋間痔瘻であろう。手術方法は単純切開で、瘻管壁を掻爬したものと思われる。 第5病日には出血も止まりガーゼを全抜去し、手術後1週間で退院した。 この「明暗」の文学的評価はさておき、漱石自身のこのような体験を通じて、医師ではない漱石の主観的な記述であるにせよ明治後期より大正時代にかけての痔瘻手術の様相を判断することができる。 「わが国古来よりの肛門疾患治療の変遷(2) ─明治・大正時代より昭和時代中期まで─」 衣笠昭 日本大腸肛門病会誌 第53巻第7号 2000年7月 から引用 |
|||||