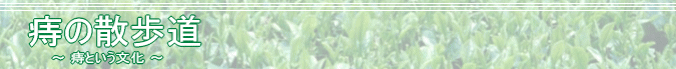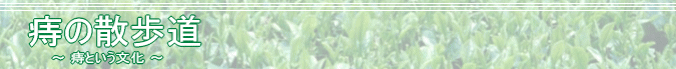■仮装人物
仮装舞踏会で被せられたサンタクロスの仮面の髯が
マッチを摺るとめらめら燃えあがる、象徴的な小説の冒頭。
妻を亡くした、著者を思わせる初老の作家稲村庸三は、
”自己陶酔に似た”多情な気質の女、梢葉子の出現に
心惹かれ、そして執拗な情痴の世界へとのめり込んでゆく。
冷やかに己れのその愛欲体験を凝視する”別の自分”の眼。
私小説の極致を示した昭和の名作。第一回菊池寛賞。
講談社文芸文庫「仮装人物」徳田秋声 一九九七年一二月五日第二刷発行 のカバーから引用
■著者 徳田秋声
明治四年金沢市で生まれる。泉鏡花と同窓。尾崎紅葉門下となり文壇デビューし、硯友社系の作家として活躍したが、後に自然主義差作家へと転換した。代表作として、「黴」「あらくれ」などがある。
同上 講談社文芸文庫「仮装人物」の「作家案内」から
この「仮装人物」を、養老孟司氏が「身体の文学史」でとりあげています。
■身体の文学史
「文学」それは人間の意識が「言葉」を手段として生み出したもの。そして「言葉」は人間の「身」が生み出したもの。しかし日本人は江戸時代以来「身体」を「言葉」から切り離し抑圧してきた、なぜなら─。芥川、漱石、鴎外、小林秀雄、大岡昇平、深沢七郎、石原慎太郎、三島由紀夫らの作品を「身体」の切り口から読み替え、文学を含めた全ての「表現」の未来を照らす画期的な論考。
新潮文庫「身体の文学史」養老孟司著 平成十三年一月一日発行のカバーから引用
■著者 養老孟司
1937(昭和12)年神奈川県生まれ。東京大学医学部卒。北里大学教授。解剖学者。主な著作に『形を読む』『ヒトの見方』(サントリー学芸賞受賞)『脳の中の過程』『唯脳論』『日本人の身体観の歴史』『異見あり』『ミステリー中毒』、対談集『脳が語る身体』『脳が語る科学』などがある。
同上 新潮文庫「身体の文学史」カバーから引用
■仮装人物
「痔」と書かれている個所を中心に抜粋します。「身体の文学史」で評論の対象となっている個所は、ピンクの文字で表記しています。
(略)
庸三の今度の訪問は、滞在期間も前の時に比べて遥かに長かったし、双方親しみも加わった訳だが、その反面に双方が倦怠を感じたのも事実で、終いには何か居辛いような気持ちもしたほど、周囲の雰囲気に暗い雲が低迷していることも看逃せないのであった。帰りの遅くなったのは、最近になって漸とはっきり自覚するよになった葉子の痔瘻が急激に悪化して、ひりひり神経を刺して来る疼痛と共に、四十度以上もの熱に襲われたからで、彼はそれを見棄てヽ帰ることも出来かね、つい憂鬱な日を一日々々と徒らに送っていた。
(略)
その晩、庸三が煩く虫の集って来る電灯の下で、東京の新聞に送る短いものを書いていると、その時から葉子は発熱して、茶の間の仏壇のある方から出入りの出来る、店の横にある往来向きの部屋で床に就いてしまった。触ると額も手も火のように熱かった。顔も赤くほてって、目も充血していた。
「苦しい?」
「迚も。熱が二度もあるのよ。それにお尻のところがひりひり刃物で突つくように痛んで、息が切れそうよ。」
「やっぱり痔瘻だ。」
庸三にも痔瘻を手術した経験があるので、その痛みには十分同情できた。彼女はひいひい火焔のような息をはずませていたが、痛みが堪えがたくなると、いきなり跳ねあがるように起き直った。それで可けなくなると、蚊帳《かや》から出て、縁側に立ったり跪坐《しやが》んだりした。
勿論それはその晩が初めての苦しみでもなかった。もう幾日も前から、肛門の痛みは気にしていたし、熱も少しは出ていたのであったが、見たところ遽かに痔瘻とも判断できぬほど、やゝ地腫《じば》れした、ぷつりとした小さな腫物であった。
「痔かも知れないね。」
彼は言っていた。その後も時々気にはしていたが、少しくらいの発熱があっても、二人の精神的な悩みの方が、深く内面的に喰いこんでいたので、愛情にも何かどろどろ滓《かす》のようなものが停滞していて、葉子の心にも受け切れないほど、彼の苛み方も深刻であった。何うかすると彼女は妹に呼ばれて離れを出て、土間をわたって母屋の方へ出て行くこともあって、暫らく帰って来ないのであったが、帰って来たときの素振りには別に変わったところもなかった。
「私を信用できないなんて、先生もよくよく不幸な人ね。」
葉子は言うのだったが、それかと言って、場所が場所だけに、争闘はいつも内攻的で、高い声を出して口論するということもなかった。
やがて其の痔が急激に腫れあがって、膿をもって来たのであった。
庸三は傍に寝そべっているのにも気がさして、蚊帳を出ようとすると、彼女は夢現のように熱に浮かされながら、
「もうちょっと居て・・・・・・。」
と引止めるのであった。
朝になると、彼女も少し落着いていて、狭い露地庭から通って来る涼風に、手や足やを嬲らせながら、うつらうつらと眠っているのだったが、それもちょっとの間の疲れ休めで、彼女が或る懇意な婦人科のK氏に診てもらいに行ったのは、まだ俥でそろそろ行ける時分で、痛みも今ほど跳びあがる程ではなかったし、熱も大したことはなかった。それがてっきり痔瘻だとわかったのは、その診察の結果であったが、今のうち冷し薬で腫れを散らそうと云うのが、差当っての手当であったが、腫物は反って爛れひろがる一方であった。そこで、今日になって葉子は別に、これも日頃懇意にしている文学好きの内科の学士で、いつか庸三をつれて病院の棟続きの其の邸宅へ遊びに行ったこともある院長にも来てもらうことにした。
その先生が病院の回診をすましてから、車で遣って来た。その時葉子の寝床は、不断母親の居間になっている、茶の間の奥の方にある中庭に臨んだ明るい六畳に移され、庸三も傍に附き添っていた。彼は診察の結果を聞いてから、こゝを引揚げたものかと独りで思い患っていたが、痛がる下の腫物を指で押したり何かしていた院長は、
「もう膿んでいる。これは痛いでしょう。」
と微笑しながら、
「あんた手術をうけたことありましたかね。」
「北海道でお乳を切ったんですのよ。また手術ですの、先生。」
「これは肛門周囲炎という奴ですよ。こうなっては切るより外ないでしょうね。」
「外科の病院へ行って切ったもんでしょうかね。」
「それに越したことはないが、何に、まだそう大きくもなさそうだから、Kさんにも診てもらったというなら、二人でやって上げてもいゝですね。」
「局所麻酔か何かですの?」
「さあね、五分か十分貴女が我慢できれば、それにも及ばないでしょう。じりじり疼痛《とうつう》を我慢していることから思えば、何でもありませんよ。」
そんな問答が暫く続いて、結局一と思いに切ってもらうことに決定した。
「痔は切るに限るよ。僕は切って可かったと今でも思うよ。切って駄目なものなら、切らなけあ尚駄目なんだ。じりじり追い詰められるばかりだからね。」
何事なく言っているうちに、庸三は十二三年前に、胃腸もひどく悪くて、手術後の窶れはてた体を三週間もベッドに仰臥していた時のことを、ふと思い出した。十三の長男と十一の長女とが、時々見舞いに来てくれたものだが、衰弱が劇しいので、半ば絶望している人もあった。神に祈ったりしていた其の長女は、それから一年もたゝないうちに死んでしまった。心配そうな含羞《はにか》んだようなその娘の幼い面影が、今でも其のまま魂の何処かに烙きついていた。若しも彼女が生きていたとしたら、母の死の直後に起った父親のこんな事件を、何と批判したであろうか。生きた子供よりも死んだ子供の魂に触れる感じの方が痛かった。それに比べれば、二十五年の結婚生活において、妻の愛は割合酬いられていると言って可かった。
翌日になって、三時頃に二人打連れて医師がやって来た。彼等はさも気易そうな態度で、折鞄に詰めて来た消毒器やメスやピンセットを縁側に敷いた防水布の上にちかちか並べた。夏も既に末枯れかけた頃で、こゝは取分け陽の光に何時も翳があった。その光の中で荒療治が行われた。
庸三はドクトルの指図で、葉子の脇腹を膝で聢《しか》と押さえつける一方、両手に力をこめて、腿を締めつけるようにしていたが、メスが腫物を刳りはじめると、葉子は鋭い悲鳴をあげて飛びあがろうとした。
「痛た、痛た、痛た。」
瞬間脂汗が額や鼻ににじみ出た。メスをもった婦人科のドクトルは驚いて、ちょっと手をひいた。─今度は内科の院長が、薔薇色の肉のなかへメスを入れた。葉子は息も絶えそうに呻吟いていたが、面を背向けていた庸三が身をひいた時には、既に創口が消毒されていた。やがて沃度ホルムの臭いがして、ガアゼが当てられた。
医師が器械を片著けて帰る頃には、葉子の顔にも薄笑いの影さえ差していた。そしてその時から熱が遽に下った。
(略)
しかし彼女は顔色もまだ蒼白く、長く坐っているのにも堪えられなかった。創口がまだ完全に癒えていないので、薬やピンセットやガアゼが必要であった。
「先生、済みませんが、鏡じゃ迚《とて》も遣《や》りにくいのよ、ガアゼを取替えて下さらない。」
「あゝ可いとも。」
庸三はそう言って、縁側の明るいところで、座蒲団を当がって、仰向きになっている彼女の創口を覗いて見た。薄紫色に大体は癒著しているように見えながら、探りを入れたら、深く入りそうに思える穴もあって、そこから淋巴液のようなものが入染んでいた。庸三は言わるゝまゝに、アルコオルで消毒したピンセットでそっと拭いて、ガアゼを当てると共に、落ちないように、細長く切ったピックで止めた。
ピンセットの先が微かにでも触ると、「おゝ痛い!」と叫ぶのだった。
「何うも有難う。」
葉子は起きかえるのだったが、来る日も来る日も同じことが繰返されるだけで、捗々しく行かなかった。
(略)
やがて涼風が吹いて来た。葉子は二度目に移って行った隣の下宿屋の二階家から、今度はぐっと近よって、庸三の直ぐ向う前の二階家に移っていた。其の頃になると、彼女も庸三の口添えで、或る婦人文学雑誌に連載ものを書きはじめていたが、一時癒るとみえた創は癒らないで、今まで忘れていた痛みさえ加わって来た。何といっても内科と婦人科のドクトルのメスには、手ぬるいところがあった。思い切った手術の遣り直しが必要であった。庸三は彼女を紹介する外科の或る大家のことも窃かに考えていたが、田舎での不用意な荒療治が、悉皆葉子を懲りさせていた。
「それよりも私温泉に行こうと思うの。湯ケ原何う?」
「そうだね。」
(略)
入院するまでに葉子の支度は可なり手間取った。(略)
葉子は湯ケ原の帰りにも、汽車のクッションで臥ていたくらいで、小田原でおりた時は、顔が真蒼になって、心臓が止まったかと思うほど、口も利けず目も見えなくなって、庸三の手に扶けられて、駅脇の休み茶屋に連れこまれた時には、まるで死んだように、ぐったりしていたものだが、漸と男衆の手で、奥の静かな部屋へ担ぎこまれて、そこで較しばらく寝んでいるうちに、額に入染む冷たい脂汗もひいて、迅い脈もいくらか鎮まって来た。彼女は何うかして痛い手術を逃げようとして、反って手術の必要を痛切に感ずるようになった。
(略)
葉子が病室で著るつもりで作った、黝ずんだ赤と紺との荒い棒縞の褞袍も、不断著ているので少し汚れが見えて来たが、十一月も既に半ば以上過ぎても、彼女はまだ二階の奥の間に寝たり起きたりしていた。その頃になると、ガアゼの詰めかえも及ばなくなって、何うかすると彼女は痛さを紛らせるために、断髪の頭を振立て、地だんだ蹈んで部屋中跳びあるいた。彼女は間に合わせの塗り薬を用いて、いくらか痛みを緩和していた。(略)
(略)
愈々葉子を病院へ送りこんでからの庸三は、遽かにこの恋愛生活の苦悩から解放されたような感じで一時吻とした。
(略)
庸三は葉子の痔疾の手術に立会って以来、兎角彼女から遠ざかりがちな無精な自身を見出した。
(略)
それと今一つは、手術場での思いがけない一つの光景が、葉子の、しかしそれは総ての女の本性を、彼の目にまざまざ見せてくれた。
庸三はその時担架に乗って、病室から搬び出されて行く葉子について、つい手術室の次ぎの室に入っていった。ゴシップや世間の噂で、既に其等の医師だちにも興味的に知られているらしい葉子は、入院最初の一日の間に、執刀者のK−博士にも甘えられるだけの親しみを感じていたが、庸三と一言二言話しているうちに用意ができて、間もなく手術台のうえに載せられた。庸三は血を見るのも厭だったし、寄って行くのに気が差して、わざと次ぎの部屋に立っていたが、すっかり支度のできた博士が、駄々ッ児の子供をでも見るような、頬笑みをたゝえて手術台に寄って行くと、メスの冷い閃光でも感じたらしい葉子は、遽に居直ったような悪戯な調子で叫ぶのであった。
「K−さん痛くしちゃ厭よ。」
博士は蓬々と乱れた髪をしていたが、「可し、可し」とか何とか言って、いきなりメスをもって行った。
「ちょっと来て御覧なさい。」
やがて博士は庸三を振返って、率直に言った。
見たくはなかったけれど、庸三は手術台の裾の方へまわって行った。ふと目に着いたものは白蝋のような色をした彼女の肉体の或る部分に、真紅に咲いたダリアの花のように、茶碗大に刳り取られたまゝに、鮮血のにじむ隙もない深い痍であった。綺麗といえば此上ない綺麗な肉体であった。その瞬間葉子は眉を寄せて叫んだ。
「見ちゃ厭よ。」
勿論庸三は一目見ただけで、そこを去ったのであったが、手術の後始末がすんで、葉子が病室に搬びこまれてからも、長くは傍にいなかった。やがて不愉快な思いで彼は病院を辞した。そして其以来二三日病院を見舞う気もしなかった。
(略)
葉子が退院して来たのは、手術の日から四十日も経ってからであった。
(略)
しかし退院して来てからの葉子には、そんな浮ついた気分はまるで無くなっていた。それに痍もまだ充分ではなかった。
「当分通わなけあならないのよ。」
彼女は畳や木の香の高い彼の部屋へ、そっと遣って来て、そんな事を言っていた。
「結核じゃないか。」
「それも幾らかあるらしいわ。沃度剤も買わせられたの。」
(略)
退院後の葉子の健康は、しかし其の頃まだ十分という訳には行かなかった。そしてそう云うことがあったから後も、何うかすると熱発を感じたが、外科ではあるが、K−博士のくれる粉薬は、直り彼女の性にあっていると見えて、いつも手提のなかに用意していたくらいだったので、少し暖かいところへ出てみたいと思っていた。
(略)
翌日も発熱が続いた。そして日の暮近くになってから、我慢し切れなくなった葉子の希望で、K−博士に来診を乞うことにした。
(略)
同上 講談社文芸文庫「仮装人物」からすべて引用 一部原文と表記が異なります。
■身体の文学史
葉子がK−博士に痔の手術を受ける場面があります。これに対し、養老孟司氏は「身体の文学史」の身体と実在の章で次のように述べています。
「それと今一つは、手術場での思いがけない一つの光景が、・・・・・・」の文章に対し、養老孟司は、
この文章が「見たくなかった」からはじまり、「やがて不愉快な思ひで」病院を去るところで終っていることが、秋声の文学的世界、あるいはむしろ一般的に、私小説的世界の辺縁をよく示している。そこには、手術を行う博士と、葉子との関係に対する、庸三のそこはかとない疑いと嫉妬が底流しているのだが、そうした心理的なヴェイルをかぶせながら、優美繊細に、そしてきわめて婉曲に、葉子の身体は秋声の世界からそっと排除されていく。
これより数頁前に、これとよく似た叙述がある。
(略)「しかし彼女は顔色もまだ蒼白く、長く坐っているのにも堪えられなかった。・・・・・・」の部分
ここではまだ、庸三と葉子の関係は、そう複雑化していない。したがって、同じような状況が、まったく感情を含めず、きわめて平叙的に描かれる。前者では、そこに博士が介在することが、叙述をまったく変えてしまう。ここでは、すでに述べた医療における制度的身体まで、話が関連しているのである。秋声についてよく言われることだが、こうした描写と構成のデテールは、ほとんど名人芸としか言いようがない。であるからこそ、こうした世界は滅びない、とも言い得るのである。」
新潮文庫「身体の文学史」から引用
原文表記とは異なる箇所があります。
|